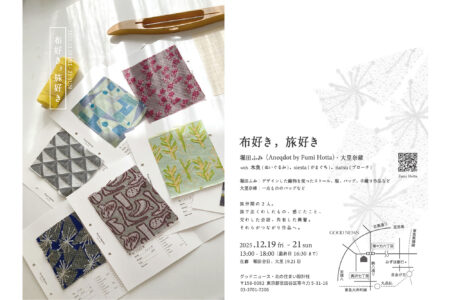先日のコラム「ダイニングテーブルTOP3」で1位に輝いたExtension Table Classic。 その製作の様子を2回に渡って詳しくご紹介します。 第1回の今日は「脚編」と題し、伸長の要となる幕板部分の製作や、組立の様子を追いかけます。

まずは材料の幅と厚みを整えていく作業。
一本一本、木の素性を見極めながら、機械に通していきます。
高速回転する刃物の摩擦熱によって反る可能性があるので、それを見越して削る面を瞬時に判断。

伸長のレールに使う部材。反りに最も気を使う部材です。

幅と厚みを整えたら、「目合わせ」という作業に移ります。 私たちは北海道産のイタヤカエデとナラというごく限られた木材しか使いませんが、それでも様々な色や木目の木に出会います。育った環境によって現れる個性であり、天然素材である証でもあります。 目合わせは、色味や表情の近いものを組み合わせて、1台分の材料をまとめる作業。 様々な表情を持つ木を、1台の家具としてまとめあげるための大切な工程です。

その後、仕口の加工に移ります。 0.1mmの精度が求められる作業。


ほぞの位置やきつさを確認し、問題ないと判断して初めて本番の材料の加工へ。


伸長システムの要、レール部分の加工。 上下・前後にはずれないように確実に治具をセットし、ゆっくりとスライドしながら溝を台形に削っていきます。

業界用語(?)で「蟻」と呼ばれる形の溝です。 古くから建築や家具の分野で使われてきた、伝統的な仕口を応用したつくり。

この「蟻溝」に「蟻レール」が入ることで、伸長の仕組みが実現します。


部材加工も終盤。面取り(角を丸く削る)加工をして、ぐっと家具のパーツらしさが出てきます。

こんな可愛らしいパーツも出来上がってきました。


いよいよ組み立て。接着力が高まるようにと、ボンドは少しはみ出るくらい入れています。 ほぞとほぞ穴の関係も、幅方向できつく効かせ、厚み方向ではボンドがわずかに残る隙間を開けることで接着力が働くように。

ある程度まで叩き入れ、

組み立て機で締め付けます。

この機械の操作は足で。足を離した後も惰性で少し進むので、繊細な操作が求められます。


ここで大切なのが、「矩手(かねて・直角)」を確かめること。 微調整をして、固まるまで置いておきます。

先ほどの小さなパーツはここに。幕板と天板を固定するパーツです。

脚の胴付面には、目合わせした番号が記されています。 その下には使い込まれた図面が。 加工寸法のメモや作業の留意点が書き込まれた、職人にとって財産とも言えるものです。


ついに脚の組み立て。脚は丸い上に角度がついているため、難しい作業になります。

脚の丸みを潰さず、まっすぐ締め付けられるようにするための当て木が活躍。

テーブルの形が現れてきました。

仕上げに移っていきます。 この日は30度を超える暑い日だったと記憶しています。 鉋がけは全身の筋肉を使うので、ハードなトレーニングのようだったことでしょう…。


このわずかな段差を

平らに削っていきます。 わずかな違いですが、天板としっかり密着させるためのこだわり。


それから、ボンドを拭き取った跡やざらつきをやすって滑らかに仕上げ。

「蟻溝」の仕上げには、

手製の道具が活躍していました。 年間数十台、このテーブルを製作しているこの職人さん。 加工方法やほぞの寸法など、わずかなことでも改良を繰り返し、より良い家具作りを目指しています。 僕は1年程この人のもとで家具作りを教わりましたが、本当に妥協を許さない、誠実な職人です。

第2回「天板編」もお楽しみに。